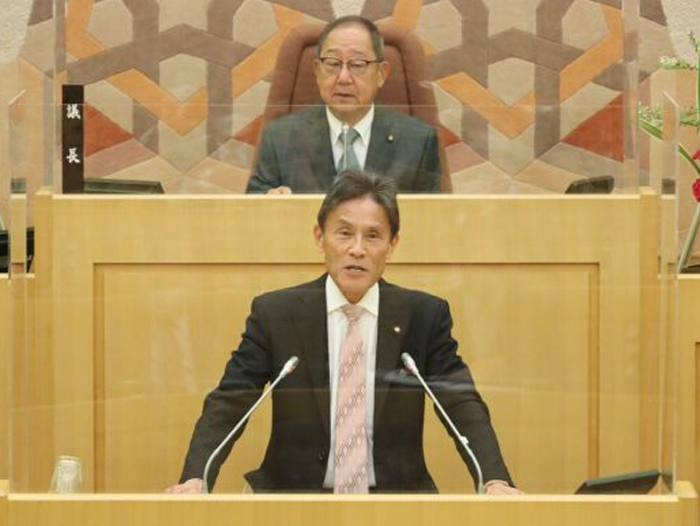第44回 おもてなし英語『学校で書道を体験』
A Japanese calligraphy club Tourist Excuse me. Is there a Japanese calligraphy club in this school? Principal Yes. You know a lot. Tourist Actually, my friend living around here told me about it. Principal That makes sense. Tourist May I observe? I'm interested in traditional Japanese culture. Principal Sure. Would you like me to guide you? Tourist Thank you so much. Tourist Wonderful! You're writing a Japanese calligraphy, aren't you? Student1 Yes, we're practicing kakizome. Tourist Kakizome? What is kakizome? Student1 Let me see…. The first writing of the New Year. Student2 We have a tradition of writing our New Year's resolutions. Tourist I see. Student2 Would you like to try it? Tourist Really? Thank you, but it looks difficult. Student2 Don't worry. We'll help you. Tourist Thank you very much for the valuable experience. Principal I'm really happy to hear that. Have a safe trip. Tourist Thank you, good-bye. 学校で書道を体験 旅行者 すみません、この学校に書道部はありますか。 校長 はい、よくご存じで。 旅行者 実はこのあたりに住んでいる友だちから聞きました。 校長 あぁ、なるほど。 旅行者 見学してもいいですか。日本の伝統文化に興味があるんです。 校長 いいですよ。ご案内いたします。 旅行者 ありがとうございます。 旅行者 すばらしい!皆さんは、習字を書いているんですよね。 生徒1 はい、書き初めの練習をしています。 旅行者 書き初め?書き初めって何ですか。 生徒1 ええっと、新年最初に書く習字です。 生徒2 私たちには、新年の抱負を込めて習字を書く伝統があるのです。 旅行者 なるほど。 生徒2 やってみませんか。 旅行者 本当ですか?ありがとうございます。でも難しそうですね。 生徒2 心配はいらないです。私たちがお手伝いしますから。 旅行者 とても貴重な体験をさせていただき感謝いたします。 校長 そう言ってもらえてうれしいです。お気をつけて。 旅行者 ありがとう。さようなら。 ...